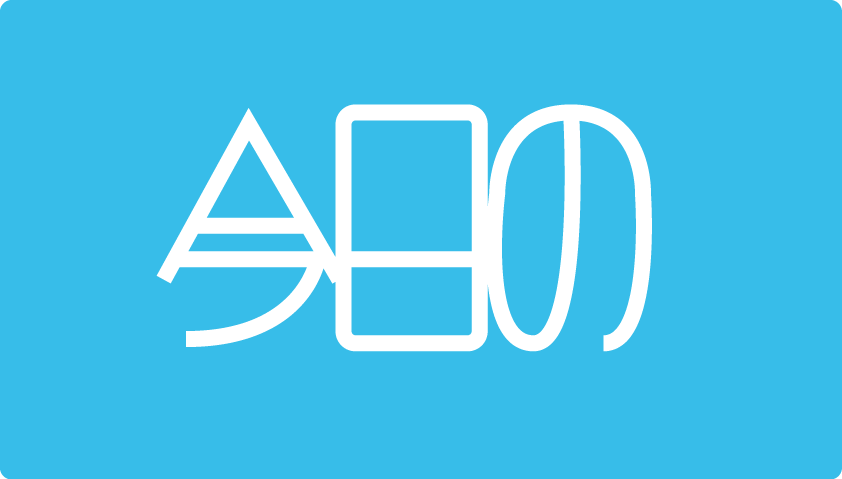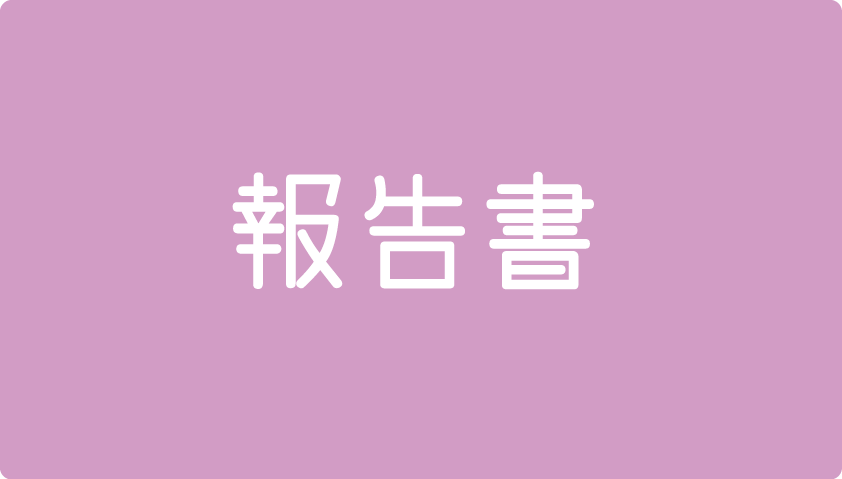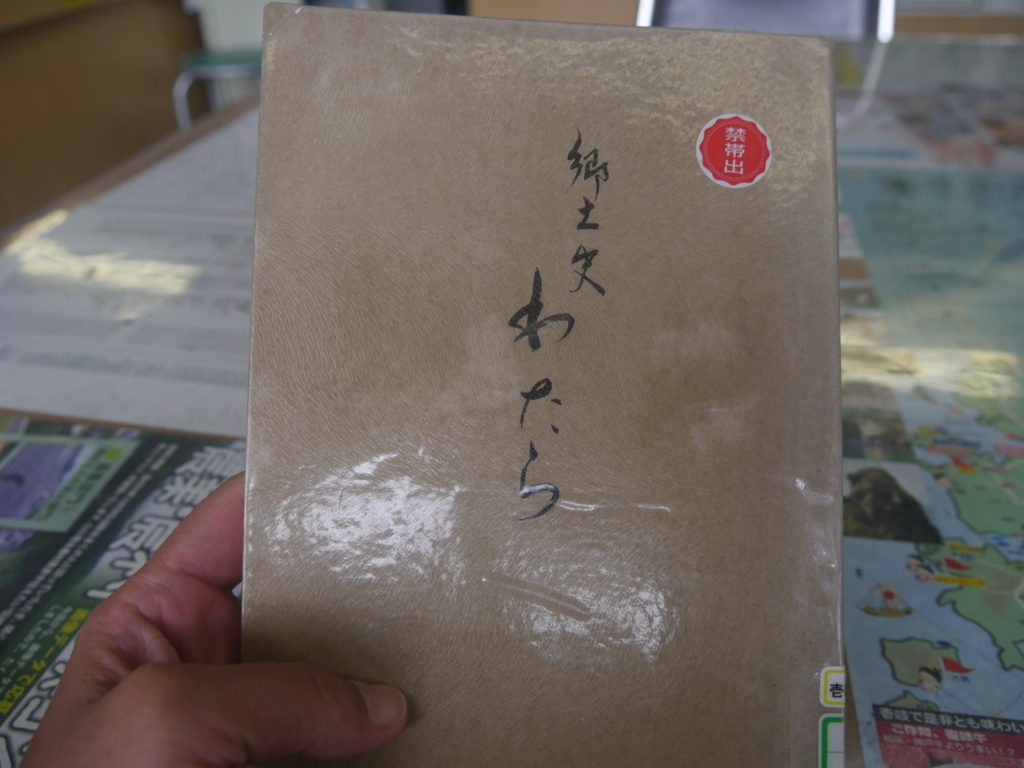「ケーマゲヒンマゲ」とは
「ケーマゲヒンマゲ」とは、壱岐にある方言で、物事を急造するという意味です。 壱岐に「ケーマゲヒンマゲ」という仮設のお店のようなものを急造し、そこを拠点として創造的な対話や制作活動を試みるプロジェクトです。
という予定でしたが、お店をつくれる場所が見つからなかった為、滞在しながら準備を進めることになりました。さてどうなるのやら。制作ノート・ニュースで日々更新していきます!レッツ ケーマゲヒンマゲ!
※現在は会期終了に伴い、日々の更新はしていません。
下記から、滞在中の記事や、インタビュー、会期が終わった後に書いた報告書などを見ることができます。
このウェブサイトは、長崎しまの芸術祭2019「アーティスト・イン・アイランド@壱岐」出品作品である、寺江圭一朗によるプロジェクト「ケーマゲヒンマゲ」です。この作品は、ウェブ・現地滞在・イベント提案の三つの柱でできています。その活動を通し、社会を志向する芸術が持つ公共性の問題に着目しようとしています。寺江は、他者にどのように近づくことができるかを試案し制作をする美術作家です

日程
滞在期間:2019年12月12日~2020年1月16日

開催場所
壱岐市
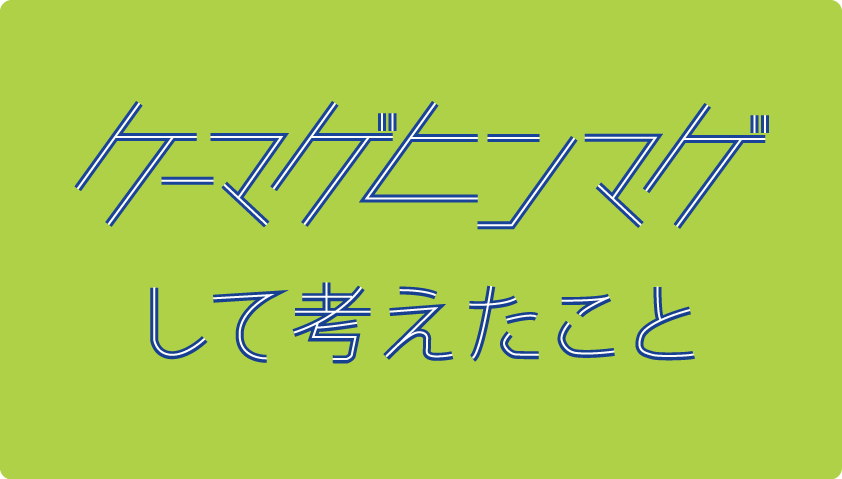
ケーマゲヒンマゲして考えたこと
この活動を通して考えたことを書きためていきます。この活動の作品の一部として、テキストを通して、「ケーマゲヒンマゲ」が何なのか明らかになっていけばと考えています。
※制作ノート・ニュースからもご覧いただけます。

互いに見る・インタビュー
この活動期間中に、展覧会や芸術、壱岐についてなど、 インタビューを申し込みます。可能な限り、壱岐の情報を発信できればなと思います。インタビューには取材という意味がありますが「互いに見る」というのが語源です。他者に近づくということは、そういうことかもしれません。僕は、美術は他者に近づくことを考えてきた歴史なのではないかと考えています。
※制作ノート・ニュースからもご覧いただけます。

芦辺浦2030年1月吉日
三味線通り
このケーマゲヒンマゲプロジェクトは、 ウェブ・現地滞在・イベント提案 の三本柱で行っていました。その最後の柱として、イベントの提案を行いました。三味線通りという行事のイメージ映像です。芦辺浦での上映イベントも開催しました。
下記リンクの作品詳細ページもご覧ください。

プロジェクト開始前の
作家コメント
壱岐は元寇によって壊滅的な被害を受け、住民は2桁代になったとも言われています。そのため各地より移住してきた人々によって街を発展させてきたという歴史があり、島内でも各地域によって独特の風習が残っています。その影響や韓国中国とも近いという地理的な条件を考えても、多様な文化が混ざり合ってきた島だと言えます。
経済と文化が、相互に破壊と再生を繰り返すことで発展していくものだとすれば、時と共に文化を構成してきた重要な物語は忘れ去られることがありそうです。しかし、今や、歴史は連続した一つの物語ではありません。それは、取り残された物語をくみ取ることで、複数の歴史を提案することや、歴史を修正することでもありません。ただ、もう一つのあったかもしれない可能性についてや、今現在から逃れた物語について思いを馳せ、回り道をすることが歴史をするということではないでしょうか。もし、その物語の中に地域の固有性を見つけることができたならば、どのように現在と結びつき、場所の力として発揮されていくのでしょうか。
壱岐でも、海底の変化により漁の形が変わり、生活のスタイルも変わってきているそうです。バブル期くらいまではアワビ漁が盛んだったとのことですが、さらに昔にはイワシ漁、そのさらに昔はクジラ漁と、主に収穫していたものは昔から変化していたようです。漁の形が変われば、生活が変わり、街が変わり、風習も変わります。そして、忘れられた祭りや唄がある。
このプロジェクトは、何かを期間限定で急造し、そこで出会う物語を中心に、街の力を再考しようとするものです。
ケーマゲヒンマゲは、様々な方との対話を通した活動を目指しています。 どなたでも見ることができ、参加することができます。「制作ノート・ニュース」の項目から、滞在期間のリサーチ、対話、制作の様子などを(可能な場合)お知らせします。